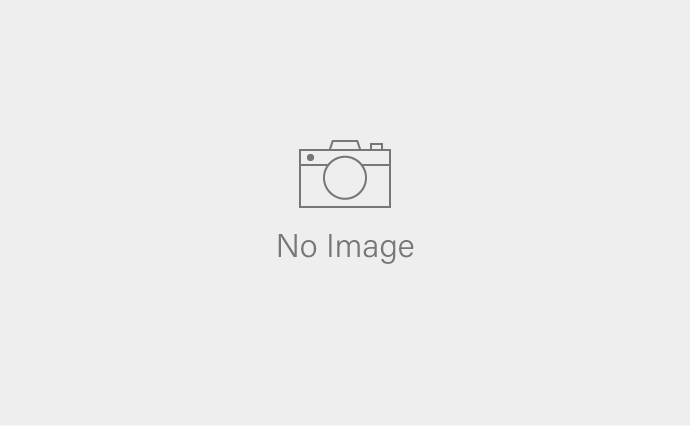「ひとり親になったけど、これからのお金が一番の不安…」 「児童扶養手当という制度があるのは知っているけど、自分がもらえるのか、いくらもらえるのか、よく分からない」 「申請って、何だか難しそう…」
この記事は、そんなあなたのための「児童扶養手当 完全ガイド」です。
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活を支える、国の大切な支援制度です。しかし、この手当は自分から申請しない限り、受け取ることはできません。
少し複雑に感じる部分もありますが、ご安心ください。 この記事では、対象者から支給額、所得制限の仕組み、そして具体的な申請ステップまで、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたの不安は「何をすればいいか分かる」という自信に変わるはずです。
そもそも児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
簡単に言えば、「ひとり親家庭の暮らしと、お子さんの健やかな成長を国が金銭的にサポートする制度」です。
【対象者】私がもらえる対象?
まず、ご自身が対象となるかを確認しましょう。以下の条件に当てはまる、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(または20歳未満で一定の障害の状態にある子ども)を育てている父・母・養育者が対象です。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡した
- 父または母が重度の障害の状態にある
- 父または母の生死が不明である
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた子どもを監護している
※ただし、日本国内に住所がない場合や、子どもが児童福祉施設に入所している場合、事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある方がいる場合は対象外となります。
【支給額】2025年度は、いくらもらえるの?
支給額は、あなたの所得(収入)とお子さんの人数によって決まります。支給には、全額が支給される「全部支給」と、所得に応じて一部が支給される「一部支給」があります。
| お子さんの人数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
| 1人目 | 46,690円 | 46,680円 ~ 11,010円 |
| 2人目の加算額 | +11,030円 | +11,020円 ~ 5,520円 |
| 3人目以降の加算額 | +6,620円 | +6,610円 ~ 3,320円 |
(例)子ども2人の場合
- 全部支給なら: 46,690円 + 11,030円 = 月額 57,720円
- 一部支給なら: 所得に応じて変動
支給は、原則として年6回(1月, 3月, 5月, 7月, 9月, 11月)に、それぞれの前月分までの2ヶ月分がまとめて振り込まれます。
最重要!【所得制限】の壁を理解しよう
児童扶養手当を満額受け取れるかどうかは、「所得制限」によって決まります。これは、申請するあなた自身と、同居しているご家族(扶養義務者)の前年の所得で判断されます。
| 扶養親族等の数 | 申請者本人(全部支給) | 申請者本人(一部支給) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
| 0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人目以降 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに38万円加算 |
【ポイント】
- 表の金額は、給与所得控除などを引いた後の「所得」の金額です。年収(額面)とは異なります。
- 元パートナーから受け取っている養育費の8割が、あなたの所得に加算されて計算されます。
- 実家暮らしの場合、同居しているご両親(扶養義務者)の所得が基準額以上だと、手当が支給されない場合があります。
ご自身の所得がいくらになるか分からない場合は、お住まいの市区町村の窓口で確認するのが最も確実です。
【申請方法】具体的な5つのステップ
それでは、実際に申請する際の手順を見ていきましょう。
ステップ1:お住まいの市区町村の窓口へ事前相談
まずは「市区町村役場の子育て支援課(または、それに準ずる課)」へ相談に行きましょう。あなたの状況を伝えることで、必要な書類や手続きの流れを具体的に教えてもらえます。
ステップ2:必要書類の準備
一般的に必要となる書類は以下の通りです。
- 申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚日などの記載があるもの)
- 申請者と対象児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 申請者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- その他、状況に応じて(所得証明書、賃貸借契約書、民生委員の証明など)
※必要書類は個々の状況によって大きく異なります。必ず事前相談の際に確認してください。
ステップ3:窓口で申請手続き
書類がすべて揃ったら、再度窓口へ行き、申請書に記入して提出します。書類の確認などがあるため、時間に余裕を持って行きましょう。
ステップ4:審査・認定通知
提出された書類をもとに、受給資格があるかどうかの審査が行われます。審査には1〜2ヶ月程度かかるのが一般的です。支給が決定すると、自宅に「認定通知書」が届きます。
ステップ5:支給開始
手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。例えば、9月中に申請すれば、10月分から手当が計算され、次の支払月である11月に10月分の手当が振り込まれます。(※多くの自治体では11月に10月分のみ、または10・11月分が1月に振り込まれるなど、初回の支給タイミングは異なります)
よくある質問(Q&A)
Q1. 離婚前でも申請の相談はできますか? A1. はい、できます。離婚後の生活の見通しを立てるためにも、離婚を考えている段階で窓口に相談することをおすすめします。
Q2. 毎年何か手続きが必要ですか? A2. はい。受給資格がある方は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。これは、引き続き手当を受ける資格があるかを確認するための重要な手続きです。提出しないと手当が差し止められてしまうので、絶対に忘れないでください。
Q3. パートで働いていても、もらえますか? A3. はい、あなたの所得が所得制限額未満であれば、働きながらでも受給できます。
まとめ:まずは「相談」という第一歩から
児童扶養手当は、ひとり親家庭にとって、経済的な安心だけでなく、「国が応援してくれている」という精神的な支えにもなる制度です。
この記事を読んで、制度の全体像はつかめたかと思います。 でも、一番大切なのは、ひとりで悩まず、お住まいの市区町村の窓口に相談に行くことです。
専門の相談員が、あなたの状況に合わせて、一番良い方法を一緒に考えてくれます。 あなたとお子さんの新しい生活を支えるための第一歩、勇気を出して踏み出してみてください。